
そう思って択一の勉強はちゃんとやってるけど、記述になかなか手が伸びない人もいるのではないでしょうか。
実はぼくも最初は記述の勉強にビビって記述の教材に手がつけれないでいました。
記述にビビってたのはお試し受験をした際、記述の問題が意味不明だったからです。
って腹の底から思いました。
でも勇気を出して記述の勉強を始めてみると意外にできるものです。
ぼくは記述で伸び悩んでいたので
「もっと早くやっておけばよかった。」
と心から思いました。
しかし、後悔先に立たずです。
ぼくはあなたにぼくと同じ後悔を味わってほしくありません。
そこで今回は記述の勉強に進めないあなたのために、一発合格できなかったぼく(二回目合格)が記述初心者が踏むべき3つの勉強ステップを紹介します。
そもそも記述の問題を解く手順はシンプルで、以下の3ステップです。
- 答案構成をする
- 論点を抽出する(何が問われているのかを見極める)
- 答案を書く
上記の3つを試験本番でしっかり行うために、普段の記述の勉強もシンプルに次の3ステップを踏めばOKです。
- リアリスティック記述式等で答案構成などの解法を学ぶ
- 解法を使ってオートマ記述式等の網羅的記述問題集を解く
- ひな形(申請例)を覚える
この3ステップを踏めば、あなたも記述で基準点を突破できる実力がつきます。
それでは詳しく勉強法を解説していきます。
関連記事:【司法書士試験独学】最強の記述勉強法はこれです。【書かずに覚える】
Contents
司法書士試験記述式の勉強法⓪:タイミング

記述の勉強を始めるタイミングは次のとおりにするのがおすすめです。
- 不登法記述:不登法択一の2周目が終わった後
- 商登法記述:商登法択一の2周目が終わった後
択一の知識があやふやでも記述を始めましょう。
記述で問われる知識は択一ほど細かくありません。
それに記述を勉強することで、登記のイメージがわき、択一の力も伸びます。
という理由で、以前は択一が1周終わったら記述をすることをお勧めしていました。
- 記述で問われる知識は択一ほど細かくない
- 記述の勉強で、登記のイメージが湧き、択一も伸びる
というのは確かに本当です。
しかし、今は択一2周目が終わるくらいが良いと思っています。
というのも、記述は択一知識が前提です。
とはいえ、不登法も商登法も択一を1周したくらいだと「わからないところがわからない」というレベルなんですよね。
(不登法や商登法を学習したことがある人なら、それらの科目の難易度から首がもげるくらい共感していただけるでしょう。)
そんな中で記述の勉強をしても効果は薄いです。
択一知識が頭にないと記述問題を解いても何が論点なのかわかりません。
(頭に論点がないと「何が論点か見極める」という段階ですらないんです。)
それに、記述でわからなくて択一テキストを参照しようにもどこに何が書いているかわからない状況です。
そして記述1周目が終わってから始めると良い理由として、以下のようにも書いていました。
また、総合点で合格点を超えても記述の足切りで泣かされる人が毎年一定数います。
なので記述対策を早めに始めるに越したことはありません。
そのため、臆せず記述の世界に飛び込んでください。
- 総合点で合格点を超えても記述の肢きりで泣かされる人が毎年一定数いる
というのも事実です。
しかし、総合点で合格点を超えて記述足切りにかかる人はまれです。
それよりも記述以前に択一に苦しめられる人が大多数でしょう。
また、記述ができない人は「択一ができていないから」という場合も多いです。
そのため、択一知識がある程度固まる段階の「目安」として「2周目終了後」とすることにしました。
人によっては「3周目終了後」かもしれません。
もちろん本試験まで時間がないのであれば「択一1周目終了後」となることもあります。
択一の勉強だけでは記述は取れません。
残された期間が短いのであれば、択一1周終了段階くらいで記述に取り組まざるを得ないのは仕方がないでしょう。
(もっとも、そのような状況は「一か八か」でその年の合格可能性を高めているにすぎません。
また、このような状況下では「力をつけること」ではなく、「先に進めること」が目的化することも多々あります。
なので、翌年合格を目指して地に足をつけて勉強するのもありです。)
こんなふうに記述勉強着手のタイミングについて語ってきましたが、どのタイミングで始めるにせよ「はじめの一歩」は誰しも億劫になるものです。
でも、本記事で書いている通りに進めれば司法書士試験記述も攻略できます。
そのため、臆せず記述の世界に飛び込んでください。
司法書士試験記述式の勉強法①:リアリスティック記述式等で答案構成などの解法を学ぶ

記述の勉強の1段階目として、解法を学びましょう。
なぜなら、記述試験の膨大な情報量を解法なしで処理するのは物凄く非効率だからです。
そして何事にも型があるように、記述の解法にも型があります。
その解法の型を学ぶのにおすすめなのが辰已さんの松本雅典先生が書いている『リアリスティック記述式』です。
本書を読めば、松本先生の緻密な思考に驚かされます。
とにかく「ミスらないための工夫」が随所に散りばめられているんです。
そのため、リアリスティックの解法を身につければ大きなミスが無くなります。
参考にリアリスティックを使ったぼくの2017年の本試験の点数は次のとおりです。
- 不登法:10.5点(35点満点)
- 商登法:34.0点(35点満点)
- 合計 :44.5点(70点満点)
- 基準点:34.0点(70点満点)
見ての通り商登法でほとんどミスがありません。
これはリアリスティックのおかげです。
(仮に不登法白紙でも基準点突破!)
「不登法ボロボロやん!」
と思うかもしれませんが、2017年の不登法は試験中に泣きたくなるほど難しくて
「わからないところはわからないから仕方がない!」
と開き直ったうえで、わかるところだけを埋めました。
そして10.5点がとれたのは「わかったところ」のミスがなかったからです。
そのため、リアリスティック記述式は偉大です。
リアリスティックなどの解法本は軽く読む程度でOKです。
サラッと読んだら実際に問題を解き始めましょう。
解法を自分のものにするには問題を解きながら解法を使うのが一番だからです。
リアリスティック使用者なら、まずはリアリスティックに載っている過去問を解いてください。
何となくでいいので、解法を見つつ自力でやりきりましょう。
過去問は難しいので当然正解が書けないと思います。
しかし、過去問は以下の3つの目的で解いてるので、ちゃんと解けなくても大丈夫です。
- 解法を学ぶため
- 本試験過去問という「敵」を知るため(敵を知り己を知れば百戦危うからず)
- ステップ2以降にやる網羅的問題集を簡単に思えるため
もちろんぼくも最初は記述過去問に手も足も出ませんでした。
ちなみに、解法本はリアリスティック以外にも市販されています。
「リアリスティックがどうも合わない。」
という人は、伊藤塾さんの山村拓也先生やアガルートさんで講師をしていた小玉真義先生が出してる市販の解法本があるのでそれらを読んでください。
また、基本的に不登法も商登法も同じ著者から学ぶのをお勧めします。
なぜなら学ぶ負担が小さいからです。
たとえば、リアリ解法の不登法と商登法は、大枠が同じです。
そのため、商登法の解法は、不登法との異同に着目すればかなり早くマスターできるでしょう。
リアリスティック記述式の使い方
リアリスティック記述式を本屋で手に取ってみたり、いったん買ってみたけどろくに中身を読んでいない人は
「分厚い。。」
と思っている人もいるのではないでしょうか。
たしかにリアリ記述は分厚いです。
しかし、解法部分は書籍の3分の1にすぎません。
しかもその解法部分は新たな「知識」を得るというより、「解法」という処理手順を知るものです。
そのため、択一テキストを読んでいたよりずっと早く読めます。
たとえば、ぼくで言うとリアリ記述式商登法を『司法試験』合格後に再度読んでみたら、2時間14分で解法部分を読み終えました。
ガッツリ『司法書士試験』の勉強をしていたときから5年以上離れた状態で読んでこの時間です。
なので、これから記述の勉強を始める初学者でも3時間か、長くても4時間ほどで読めます。
そのため、臆せずリアリ記述式を読んでみてください。
リアリ記述式で解法を読んだ後は2問の過去問を解きましょう。
この際のおすすめは、1問目を2回解いてから2問目に行くことです。
過去問はもともと超難しいです。
その過去問の1問目を解いて「できない体験」をして、すぐに2問目に行って「できない体験」をすると精神的にもきついんですよね。。
一方で1問目を2回連続で解くと、同じ問題だし、この間解いたことなので、2回目は1回目より少しはできるようになっています。
この「少しできた体験」が今後学習していくうえで貴重です。
さらに、実際に「少しできた」ことで解法も実際に少し定着しています。
なお、このように過去問はできれば最初に2問解いてほしいのが本音です。
しかし、残り時間との兼ね合いから、解く過去問を1問に絞るのもOKです。
また、巻の最後についている「ノック」は、とりあえず飛ばしてください。
ぼくが司法書士受験生のときは、まだなかったくらいだからです。
そのため、まずは解法を習得するために過去問を解いて、ステップ2の網羅的記述問題集に移りましょう。
追記:リアリ記述式(解法本)で跳ねた!
オートマ記述を使っていたけど振るわなかった方が、リアリ記述式で跳ねたご報告をいただいたいので共有します。

このあずさんすごいです。
こうやって何でも真似する人は成果が出ますね。
あと、『夢をかなえるゾウ』も読みやすくて個人的にすごくおすすめです。
司法書士試験記述式の勉強法②:解法を使ってオートマ記述式等の網羅的記述問題集を解く

司法書士試験の記述式にはパターンがあります。
出題のパターンは無限にあるように思われます。
しかし、結局はいくつかの論点の組み合わせにすぎません。
そのため、いくつかの限られた論点をしっかり学んでおけば、あとは組み合わせなのであらゆる問題に対応できます。
リアリスティック記述式が「解法の型」を学ぶものなら、網羅的記述問題集は論点の型を学ぶものです。
そこで、ステップ1を終えたらステップ2として、解法を使いながら網羅的記述問題集で基本論点を学びましょう。
網羅的記述問題集としておすすめなのは、TACさんの山本浩司先生が書いている『オートマ記述式』や松本先生の『リアリスティック記述式問題集 基本編』です。
ぼくはオートマ記述で合格したので、オートマ記述で解説を進めていきます。
(松本先生はぼくが一番尊敬している講師の一人なので、先生の『リアリスティック記述式問題集 基本編』も間違いありません。)
オートマは問題数が不登法が42問、商登法が30問(+合同会社)と決して多くないですが、必要十分です。
ぼくはオートマのほかにもハイレベル問題集を使いましたが、ハイレベル問題集は論点を学ぶのではなく本番形式の問題を解く「練習」のために使いました。
そのため、オートマを侮らず愚直に繰り返して記述のパターンを頭、いや体に叩き込みましょう。
ちなみに不登法の「応用の部」は難しすぎるので解かなくてOKです。
「応用の部はやらなくていいんで基本の部を何回もやってください」
と山本浩司先生も講義で言ってると聞きます。
要注意ですが、商登法は
●応用編
●実戦編
もしっかりやってください。
合同会社もやりましょう。
オートマを解いてみると最初は論点を見抜けなくて自分にイライラすることの連続です。
しかし、1周目2周目で解けないのは当たり前です。
オートマは天才の山本先生が作ってるものなんですから。
でも、その天才の問題が解けるようになったときはすごく力ついている証拠です。
本試験でもかなり戦えます。
なので、オートマの問題が解けるレベルになるようとにかく反復です。
また、問題を解く際は解法をできるだけ使ってください。
たとえば、オートマの問題は本試験の形式と少し違うのでリアリスティックの解法をそのまま全部使うことはできません。
しかし、登記の権利関係の図を描くなどの答案構成はできます。
そのため、答案構成だけは絶対にしましょう。
最終的にはリアリスティック等の解法を見ないで、自力で答案構成をしないといけません。
ただ、はじめは解法を覚えるだけでも苦労します。
そのため、最初のうちは問題の脇にリアリスティック記述式等の解法本を横に置いて、適宜参照して答案構成等ができればOKです。
リアリスティックの解法でオートマを解きまくると「解法の型」と「論点の型」がいっぺんに身につきます。
一石二鳥でお得なのでぜひやってください。
オートマ記述とリアリ記述式問題集のどちらが良いか?
両書籍はそれぞれ良いものです。
しかし、両方を完璧にしようなどとは思わないでください。
1冊を完璧にするだけでも大変なのに、2冊完璧にしようとすると受験が超長期化するからです。
(1冊をしっかり仕上げた段階で、記述問題を解く素材としてもう1冊をやるのはありです。
ただそのような段階では、本試験形式の問題演習をすべきなので、もう1冊をやるのはあまり考えられません。)
それでは、両者のどちらを選べばよいのでしょうか?
結論を言うと、
- オートマテキストを使っていて、解法はリアリ以外なら、オートマ記述一択
- リアリテキストを使っていて、解法もリアリなら、リアリ記述一択
です。
なぜなら、著者の思想の一貫性を持たせたほうが良いからです。
どういうことかというと、教材には著者の思想が反映されています。
そして、教材をやり込んで著者の思想も含めて吸収することで、受験生としてのレベルが上がります。
たとえば、オートマテキストをやり込んでいるなら、著者の山本先生の思想もインストールされていき、脳みそが山本先生みたいになるということです。
山本先生の脳なら司法書士試験に受かりますよね?笑
「思想」という抽象度の高いことを吸収するので、個別具体的な知識ではありません。
なので、記憶に頼らず
「山本先生ならどう考えるか?」
ということが無意識に起こるようになり、見たことがない問題でも自然と正解を導き出せるようになります。
実際にぼくも
「この問題わからないな。」
と思うような最後の2択になるような問題でも、驚くほど正答率が高かったです。
これは山本先生の思考をインストールして、山本先生の脳を手に入れていたからでしょう。
ちなみに、「無意識」なのは、
- 自分の思考=(≒)山本先生の思考
になっているからです。
(自分の思考を毎回意識している人はいませんよね?)
話がそれました。
しかし、オートマ記述とリアリ記述問題集のどちらにすれば良いかは、「思想」の話で分かったと思います。
というのも、以下のようになりますからね。
- オートマテキスト(山本先生)を使っていて、解法はリアリ以外(松本先生以外)なら、オートマ記述(山本先生)一択
- リアリテキスト(松本先生)を使っていて、解法もリアリ(松本先生)なら、リアリ記述(松本先生)一択
それじゃあ、上記の両方に当てはまらない場合はどうすればいいの?という話ですよね。
ぼく自身は
- オートマテキスト(山本先生)を使っていて、解法はリアリ(松本先生)
でした。
この場合はどっちでもいいです。
どちらか迷ったら、オートマ記述にしてください。
なぜなら、オートマのほうが歴史が長く、受験生間でのシェアが高いからです。
相対評価の試験では、「受験生間でのシェア」は重要な要素です。
あと、ぼく自身がオートマ記述を使って合格したのも大きいですね。
司法書士試験記述式の勉強法③:ひな形(申請例)を覚える

ステップ3は「ひな形(申請例)を覚える」です。
このひな形を覚えて書かないと本試験で点が1点も入りません。
なので、ひな形もめちゃくちゃ重要です。
「記述の問題を解いていれば、ひな形は自然に覚えちゃう。」
という人もいるようですが、ぼくのように自然に覚えられない人は別途ひな形集等でひな形を覚えましょう。
ぼくはひな形集に『オートマひながた』を使ってました。
「オートマシリーズを使ってたから。」というのが理由ですが、オートマひながたはおすすめです。
オートマひながたは登記実行後の記録が書いてあるのでイメージがわきやすいです。
それに、説明もシンプルにまとまっています。
とはいえ、ひな形に何を使うかはそこまでこだわる必要はありません。
そもそも可処分時間が少ない兼業受験生であれば、ひな形集をぼくは受講生に非推奨にしています。
ひな形集の代わりにテキストに載っているひな形を覚えていただいています。
たしかにひな形集のほうが網羅性に優れています。
テキストのように「飛ばし飛ばし」にならないのもメリットです。
しかし、「ひな形集」の性質上どうしても優先度の低いひな形も載っているんですよね。
それなら「選択と集中」の観点から可処分時間が少ない兼業受験生は、数は少なくても重要なひな形をテキストで学ぶべきです。
あとは、オートマ記述などの網羅的問題集を通して能動的に学びましょう。
ちなみに、ぼくの受講生で行政書士不合格から7ヶ月で合格した藍沢梨夏さんもひな形集は使わずに、オートマテキストのひな形を覚えて合格されています。
ひな形の勉強を始めるタイミングですが、解法と論点を学んだあとで大丈夫です。
網羅的問題集を1周させたくらいからひな形もボチボチ覚え始めましょう。
また、ひな形を覚えるときはなるべく短い文言を追求すべきです。
覚える分量は短いほうがいいし、時間に追われる本番を考えても書く分量は短いほうがいいからです。
たとえば、オートマテキストにも登記申請例が載ってますが、オートマひながたと文言が少し違ったりします。
そんなときにオートマテキストに書いてる文言のほうが短くて覚えやすかったら、オートマテキスト通りに覚えてください。
そのほかにも各予備校の模試や答練を受けていく中で楽に書けそうな文言を見つけることもあると思います。
「伊藤塾の模範解答の書き方は書きやすそうだな。」
「TACのこれもいいな。」
みたいな感じです。
そんなふうにいろんなところから「いいとこどり」をしてひな形を覚えていきましょう。
この「いいとこどり」のためにおすすめが、リアリスティックの不登法や商登法の択一テキストです。
なぜなら、著者の松本先生が過去問を分析しているので、減点されず、かつ最もコンパクトに書けるひな形を教えてくれているからんですよね。
そのひな形を知るために課金する価値はめちゃくちゃあります。
あと開示請求をしてわかったこともあるので以下の記事もご参照ください。
>>【司法書士試験】開示請求した記述の答案が届きました。【わかったのはこの3つ!】
司法書士試験記述式のひな形は音読して覚えよう

ひな形を覚えるのに「書く感覚」は必要ありません。
ひな形は声に出して言えればそれで覚えたことになります。
そして覚えるにはとにかく『繰り返し』が大切です。
たしかに1回書くのと1回音読では、前者のほうが覚えは良いかもしれません(音読しながら書けば一番覚えやすいでしょう)。
しかし、1回書く間に何度も音読できます。
つまり、音読のほうがたくさん繰り返せるので、効率的に覚えられるんです。
なので、ひな形は是非音読で覚えてください。
まとめ:司法書士試験記述対策を今すぐ始めよう

「記述は択一と勝手が違う」という感覚は正しいです。
択一の知識があっても記述は書けません。
そのため、択一を2周したくらいのタイミングで記述対策を始めましょう。
記述の基準点は基本を抑えれば突破できます。
基本を抑えるにはとにかく「型」の徹底です。
なので今回紹介した3つの型を繰り返して自分のものにし、記述の基準点を突破してください。
ちなみに、記述以外にも独学に適した教材が知りたい人は、ぼくが独学で使った教材を下記記事にまとめたのでよかったらどうぞ。
 ︎この記事をシェアしませんか?
︎この記事をシェアしませんか?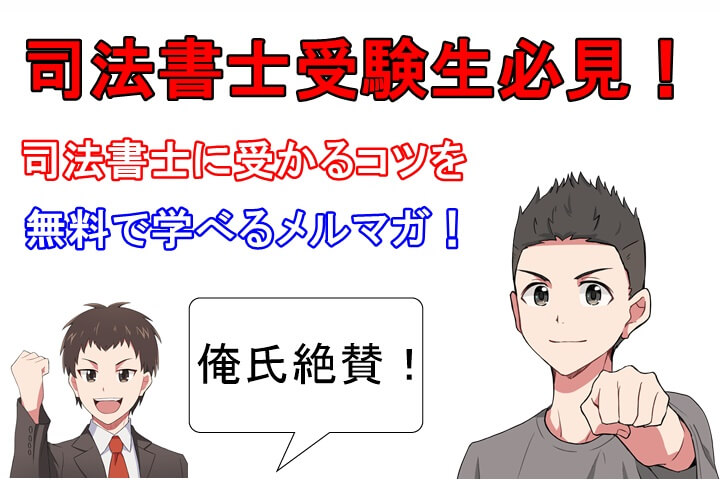






めちゃくちゃ参考になりました。
ありがとうございます。
ミポリンさん、ありがとうございます。
ホントこの通りにやれば勝てるのでぜひやってみてください(^^)
リアリスティックで解法を学んだんですけど結局付属の過去問を解けずに落ち込みました。
図を書いたり別紙に蛍光ペン塗ったりとかはあらかた出来るんですけど「だからなに?」って感じで。結局なんの登記を申請するのかわからず、答えを見てもこんなの書けるようになるのか?って感想です。
ジョンさんはリアリスティック記述式で記述の学習を始めたんですね!
多くの人が記述にしり込みする中で素晴らしいです(^^)
ちなみに、ジョンさんは今どの学習段階でしょうか?
ステップ1であれば、ステップ2のオートマ記述式に行ってください。
リアリスティック記述式だけでは、論点知識が頭にないまま解くことになるので解けないのは当然です(>_<) よろしくお願いします!
お返事ありがとうございます。
コロ助さんの仰るステップで言うとそうですね、ステップ1と言って差し支えないかと思います。
厳密に言うとオートマ基礎テキストを繰り返し読み、オートマ記述式をチョロっと見て見たものの撃沈、リアリスティックがいいという評判を頼りに解法を学ぶものの、これをどう活かせばいいのだろう、、、という状況です。
今はオートマ不動産登記法の登記申請例を暗記しながら会社法テキストを読み込み、登記事項や記述式に使いそうな知識に付箋を貼って復習の足がかりを作っています。
現状についてかしこまりました。
それでは、リアリの解法でオートマを解いてみてください!
また、お手を煩わせてしまい、失礼しました。
コメントは承認制にしていたので、初めてコメントされる場合はすぐにはコメントが反映されないようになっていました。
(ジョンさんは1回目はメアド無しでのコメントで、2回目以降(15日の夜)はメアドありだったので、別人と判断されたのだと思います。)
そして今回の件から承認制をやめて、メアド記入必須に設定し直しました。
これからもよろしくお願いします!
オートマ不登法記述式を2問分解いてみました。だいぶ前に解いた時より不登法の読み込みが進んだおかげか、1問目、2問目ともになんとなく方向性としては当たらずも遠からずな内容を書けました。
もっとも1問目は解法の使いどころがなく、2問目でチョロっと甲持分の相続と抵当権が追加される図を書いただけであまり恩恵を感じられては無いのですが汗
この調子でいいのでしょうか。1日2問ずつ進めようかと思ってます。
ジョンさん
(返信数が既定の数を超えたためか、返信ができないので新たなコメントとして返信させていただきます。)
不登法択一知識が記述の前提にあるので、その感触は間違いないと思います。
また、解法の使いどころがないとのことですが、権利の図も書けないでしょうか。
それと、最初のうちは何も見ないで解法通り解くのは難しいので、リアリ記述式をを見ながらオートマを解くようにしてくださいね!
やっていくうちにわかっていくこともたくさん出てくるので、とりあえず進めてみてください(^^)
お久しぶりです。現在不登法記述式22問目まで終わらせました。どの問題でも「全くなんの登記を書けばいいのか分からない」ということは無いので多分順調だと思います。
ですが商登法の復習法について困ってます。不登法と同じく付箋を貼って数日おきに確認するやり方にしてるのですが、不登法と比べて個性豊かな添付書類等が多く、かなり苦戦してます。何かいい方法はありますか?
(ぼくの疲労もあってか)ジョンさんのことについてわかりかねる情報が多すぎてコメントに書いていただいた情報だけでは何とも言えないです。
お忙しいところ大変失礼しました。
弱気になってしまい、つい誰かに頼りたくなってしまう気持ちから質問を重ねてしまいました。おっしゃる通り数行の文章では私の現状を正確に把握して頂くことは困難ですし、曖昧なアドバイスを送ることは私のためにならないというコロ助さんのご配慮を感じ、大変恐縮です。もう少し自分で頑張ってみます。
コロ助さんお世話になっております。
私もコロ助さんの方法で取り組んでおります。
リアリ、オートマ、オートマ雛形。
過去問は正直難しいですし、テキストも分からない事も多いです。(意外と商業登記は論点掴みやすいかもと、完璧に見抜いたり書けたりは難しいですが、、)
再度この記事を拝見させていただき、今一度信じて突き進もうと思います。
ありがたいことに先日尊敬する司法書士の先生の実務に関わることもあり、モチベーション保ちながら進もうと思います。こういう経験も大切ですね。
正直記述で本当に書けるのか?と思っておりますが、自分のことも、コロ助さんの方法も信じてやり切ろうと思います。
いつも勇気をいただき感謝します。
ヒロミチさん、相変わらず素晴らしいですね!
やることは本当にシンプルです。
あとは結果が出るかわからない中でも愚直にやり続けることが非常に大事になってきます。
司法書士の先生の実務にかかわることもあったようですし、ヒロミチさんならやり遂げられます!
ちなみに、記述過去問は難しいので最初はリアリに載っているものだけを解くにとどめて、基本的にはオートマ記述にある問題を繰り返して完璧に近づければOKです。
記述過去問を本格的にやるのは4月以降の直前期ですね。
コロ助さん
本当にありがとうございます!
今は記述過去問はリアリに留めておきます、他は解ける気がしません。。
とにかく記述のみならず択一も信じてやり遂げるしかないですね!
オートマがボロボロになるまでやってみます。
引き続き宜しくお願い致します。