
こんにちは。コロ助(@korosuke1ban)です。
ぼくがとった択一の勉強法について、記憶が薄れていく前に書いておこうと思います。
ぼくが択一対策で使用した教材は、テキスト(オートマシステム・デュアルコア商法・プレミア憲法)とでるトコ一問一答です。
テキストを徹底的に回してインプットとアウトプットをしつつ、でるトコでもアウトプットをしていました。
記述の勉強法はこちら。
>>【司法書士試験独学】ぼくがとった記述の勉強法はこれです。【書かずに覚える】
Contents
テキストでインプット・アウトプット

ぼくが勉強を始めたのは民法からです。
そこから
民法→不登法→商法・会社法・商登法→民訴系
というふうに進んでいくのではなく、
民法→不登法→民法→不登法→商法・会社法・商登法
というふうに先に進みつつも前に戻って復習するというようにやってました。
前に戻らずに全科目1周させると、ずっと前に覚えたことが抜けてしまい、いつまでたっても覚えられないと思ったからです。
(でも、マイナー科目に入ってからは戻らずどんどん進んでました。このやり方じゃ試験に間に合わないと思いました。)
また、各科目内においても
代理→時効→意思の欠陥→制限行為能力→瑕疵ある意思表示
というふうにどんどん進んでいくのではなく、
代理→時効→代理→時効→意思の欠陥→代理→時効→意思の欠陥→制限行為能力
というふうに単元を行ったり来たりしながら進めていました。
その単元を復習するために最低でも3回は前に戻るという感じです。
また、復習するときはただ読みこんでインプットするのではなく、アウトプットもしていました。
テキストの重要なポイントを思い出しながら読むことによって、それがアウトプットになります。
詳しいテキストアウトプットの仕方は以下の動画で話しました。
※ぼくのYouTubeは動画下の概要欄の目次から任意の場所に飛べます。
ただ、本動画を見たことがない人は全部見るのを推奨します。
一部だけを見ても断片的な情報を得たにすぎず、きちんと物にできないからです。
司法書士試験テキストの使い方

テキストの具体的な使用法について見ていきます。
アンダーライン
ぼくはテキストにアンダーラインを引いて、そこにどんなことが書いてあるのか一目でわかるようにしていました。
アンダーラインの色は2色です。
- 赤:結論
- 青:趣旨・理由


このように色に意味付けをしていれば、瞬時に大事なところがわかるので復習のスピードも高まります。
一方で、まっさらなテキストだとどこが大事なのかよくわかりません。
なので、アンダーラインなりマーカーなりテキストに線を引くことは激しく推奨します。
といっても、テキストは自分しか見ないものなので、線引きのルールは神経質にしすぎる必要はありません。
そのため、あまり気負いすぎずに線を引いていただければと思います。
線引きでミスが怖いという人はフリクションボールペン(消せるボールペン)がおすすめです。
テキストの線引きについてもこちらで話しています。
関連するページ数
テキストを読んでいて、「関連する知識」、「何か似てるなーと思う知識」がほかのページにあればそのページ数をテキストの余白に書きこむようにしていました。
「-P96」というふうにです。
書くのはあくまでもページ数だけで、知識そのものは書きません。
ページ数を見て関連する知識が何なのかを思い出すのが勉強になります。
このように関連する知識のページ数を書きこんでいけば、
「-P96」、「-p300」、「-不登P201」、「-商P283」
と4つも5つも関連する知識を余白に書くことがあります(違う科目の知識を関連付けるときはページの頭に科目名を書いていました)。
そうすると、1つの知識を勉強しているときにほかの知識を4つも5つも一度に復習できます。
しかも、関連付けられた記憶は強固になりやすいということが言われています。
なので、この勉強法は最強です。
でるトコ一問一答でアウトプット

テキストで3回復習したらでるトコ一問一答をやっていました。
4回もテキストをやりこんでおけば、かなり記憶が定着しているはずです。
しかし、いつもテキストばかりやっていては本当に知識がついているのかわかりません。
なので、でるトコで問題を解くようにしていました。
でるトコでアウトプットすることによって記憶の定着もさらに強固なものになります。
また、テキストには載っていない論点もでるトコでたまに出題されているので、そこはでるトコで確実に押さえていました。
司法書士試験において、でるトコは最強の教材のひとつだと思います。
試験に出る論点をあそこまで簡潔かつ網羅的に一問一答形式でまとめているのは秀逸です。
ほかの一問一答形式の問題集をガッツリやったことがないので比較できませんが、ぼくはでるトコを強くお薦めします。
でるトコを手にとったことがない人はぜひ本屋さんに行って試しに2、3ページ問題を解いてみてください。
テンポよく解けるので、はまる人が出てくるはずです。
ちなみに、こちらはぼくが以前サポートした方からいただいた合格報告です。
令和1年合格目標として以前サポートした方から司法書士試験合格報告をいただきました
この方は令和1年は残念な結果で、お仕事の関係からコロナで令和2年・3年は受験を見合わせての今回の合格でした
当たり前ですが、この方の頑張りが99%以上です
でも少しでも合格への力になったなら嬉しいです(^^) pic.twitter.com/MkUrlo65Og
— コロ助@司法書士試験コーチ (@korosuke1ban) November 6, 2022


兼業フルタイムの方なので、素晴らしいです。
ただしでるトコは、やりすぎ注意です。
でるトコは本当にポンポン解けるため、癖になってしまうことがあります。
一番大切なのはテキストなので、テキストをおろそかにしないようにしましょう。
オートマテキストやでるトコ以外でもぼくが独学で使用した教材をまとめました。
「必要最小限の教材が知りたい!」
という人はぜひ参考にしてください。
>>【保存版】司法書士独学でコロ助が使用したテキスト・問題集まとめ
動画もあります↓
司法書士試験の過去問集はやらなかった

ぼくは過去問集を解きませんでした。
やったのはオートマテキストに載っていた過去問だけです。
時間が限られていたことと合格最低点をとるのに過去問は必要ないと思ったのが理由です。
詳しくは以下の記事を参照ください。
>>【司法書士試験】択一の過去問は当然必要!じゃなかった・・・【テキスト派】
司法書士試験の直前期対策

試験直前期は前に戻るということはせず、どんどん先に進んでなるべく多くの科目に触れるようにしました。
司法書士試験は科目が多く範囲が広すぎてたいへんですが、ここは気合です。
テキストもでるトコもガンガン回しました。
本試験で問題を解くときに、どの科目でも「久しぶり感」がないようにすることが大切です。
また、直前期にやって良かったことをまとめたので下記記事もよかったらどうぞ。
>>【司法書士試験】直前期にやってよかった6つのこと。【後悔のないように】
司法書士試験受験の反省点

自分としてはもっとも正しいと思われるやり方で勉強してきました。
しかし、多少遠回りしたところもあったと思います。
たとえば、テキストをやるときに「前に戻りながら進めていく」ということを最初からぼくはやっていました。
一度覚えたことを忘れたくないがために何回も何回も前に戻りました。
しかし、今思えば戻りすぎた感がります。
というのも、覚えたことを忘れるのは当たり前で仕方がないからです。
そのため、ある程度のことを理解すれば、とりあえず前に進んで全科目を1周させて「全体像を把握する」というふうにしたほうがいいと思います。
(もう少し細かく言うと、主要四科目を2周して、マイナーを1周。)
司法書士の科目はそれぞれ独立しているようで、意外と繋がっています。
単体の科目で見たときに理解できないことでも、ほかの科目をやってみることで理解できるようになったこと・理解が深まったことがありました。
それに、テキストを一度1周させないと1周させるのにどれくらいの時間がかかるのかがわかりません。
なので1周させないと長期的な勉強計画が立てづらくなります。
これから勉強を始める人やまだ勉強を始めたばかりの人はとりあえず全科目を1周させるということをまずはやってください。
さいごに:司法書士は司法試験以上の難関だからすごい!

司法書士の択一は予備試験や司法試験以上の難易度です。
実際にぼくは予備試験や司法試験を受けて合格しましたが、択一は司法書士と比べたら簡単すぎました。
司法書士はそれほど超難関試験です。
なので、「司法書士の勉強をしている自分はすごいんだ!」とまず思ってください。
本当にすごいことなんですから。
そして、超難関試験と向き合う自分に誇りをもって最後まで突っ走ってください。
やってきた努力が成果に直結するのが択一試験です。
関連記事:司法書士試験22歳で上位合格までのコロ助の法律勉強歴【独学で受かるのか?】
2022年11月4日:司法試験合格後に追記

司法書士試験合格後に、認定考査試験7位合格。
予備試験最終試験4位合格。
司法試験一発合格
こんなふうに司法書士合格後に勉強を重ねていく中で、ぼくは勉強法をブラッシュアップさせてきました。
そして、「司法書士試験受験の反省点」を上記に記しましたが、より言語化したものを今回書いておきます。
概要
ぼくは司法書士受験時代は復習の間隔を詰め過ぎたと思ってます。
たとえば、3日前の復習をサラリと、学習初期は2日前の復習と1日前の復習をある程度ガッツリやってからその日の分というふうにしていました。
(学習初期はこれでも悪くないかもしれませんが、後述する方法がベストだと思います。)
でも今ならそういうことはしません。
本試験までの時間は有限(トレードオフ)なので、前に戻った分だけ、先に進めなくなるからです。
そうすると、結局1周して戻ってくるのに時間がかかってしまいます。
つまり、前に戻って復習間隔を詰めているようで、長期スパンで見れば、復習間隔をかなり空けることになるんです。
それに、復習の間隔はある程度間を空けたほうがいいこともわかっています。
「忘れたころにする復習」が効果的とされているんです。
(勉強法については『進化する勉強法』が参考になります。)
学習段階によって復習間隔を変えよう
話を整理すると、学習段階によって復習間隔を変えましょう。
- 学習初期:復習間隔を詰める(集中学習)
- 学習中期以降:復習間隔を空ける(分散学習)
まず学習初期は、記憶よりも理解重視でいくべきです。
そして、理解するための勉強としては、学習間隔を空けない「集中学習」が良いとされています。
なので、インプット重視の最初の学習期間で復習の間隔を詰めるのが良いです。

ただ、学習初期のインプット(理解)段階を終えた後は、記憶のためにアウトプット重視に移行したほうが良いです。
そして、記憶するためには、間隔をある程度空けて学習したほうが良いとされています。
これは「集中学習」と対になる概念で、「分散学習」と言います。
「間隔をある程度空けて」というのは漠然としていると思いますが、たとえば、司法書士の全範囲を終えるのに2ヶ月かかるなら2ヶ月間空けるのがおすすめです。
「期間を空けすぎるのは良くない。」
というのは確かにそうです。
しかし、時間はトレードオフなので、何かをやれば何かができなくなります。
つまり、前に戻ったらそのぶん進みが遅くなって、また1周戻ってくるのに時間がかかって「長期の視点」で見ると結局どこかで期間が空いてしまうんです。
ぼくは大局的に物を見るのが何事においても重要だと思っています。
なので、ぼくは基本的に前に戻らない勉強を推奨しています。
学習初期の理解重視段階の具体的復習法
先に述べている通り、理解重視の場合は「集中学習」の観点から復習間隔は詰めたほうが良いです。
そのため、初学者でオートマを使って独学する場合、次のように進めてみてください。
1日目
- オートマテキスト読み込み(インプット重視)
※じっくり読むのは大事だけど、完璧は目指さない。
※明日も明後日も同範囲をやることを考えると良い意味でいい加減になれる。
※参考問題演習や線引きも含めて、だいたい1時間~1時間30分あたり10ページが目安。
※講座受講者はここは講義視聴。
- テキストにある参考問題(アウトプット)
※参考問題で問われたテキスト該当箇所に線を引く
※オートマテキストではない人は参考問題がテキストに載っていないので、厳選された過去問集を推奨
※オートマユーザー以外かつ予備校講義視聴者は、以下の理由からこの段階で無理に過去問を解かなくても大丈夫
(独学だと「読む」という能動的な姿勢なので、すぐに問題を解きやすい。
一方で、予備校講義は「聴く」という受動的なものなので、問題をすぐには解きにくい。
ただ、オートマテキストだと「テキストに載っている参考問題も含めて一体」という形だから、オートマユーザーは講義視聴者でもオートマテキスト記載の参考問題はすぐに解いてよいかも。)
2日目
- オートマテキスト復習(インプット重視。できればアウトプット)
※じっくり読むのは大事だけど、完璧は目指さない。
※明日も同範囲をやることを考えると良い意味でいい加減になれる。
※初学者なので1日目と同じくらいの時間になるのは多少仕方がないが、1日目より時間がかかれば完璧主義に陥っている証拠。
- 参考問題(アウトプット)
※参考問題で問われたテキスト該当箇所に線を引く。
- 今日の範囲の1日目をやる
3日目
- でるトコを解く(アウトプット)
※でるトコで問われたテキスト該当箇所に線を引く。
※ここで少しだけ「できる!」を体感してほしい。
ただ、できなくても最初だから当たり前。「勉強が未熟だった」に気づけて間違えてもどの道プラス!
- サラッとテキスト復習(インプット重視。できればアウトプット)
※でるトコで出たところを中心にざっとさらう感じで、あまり時間を書けない。
※オートマユーザー以外かつ予備校講義視聴者は過去問2回目を解くのがおすすめ。
- 昨日の範囲の2日目をやる
- 今日の範囲の1日目目をやる
4日目
- おとといの範囲の3日目をやる
- 昨日の範囲の2日目をやる
- 今日の範囲の1日目をやる
(以下繰り返し)
※長期的な学習の進め方は、メルマガ1通目で案内している下記記事をご参照ください。
>>【メルマガ限定記事】底辺大学生から22歳独学で受かったぼくの司法書士試験合格までの道【勉強スケジュール】
本試験まで時間が無ければどうするか?
もし本試験まで時間が無いのであれば、3回目の復習をカットするしかないと思います。
でるトコもやったほうが理想ですが、一応オートマテキストで網羅されていると言えるからです。
あと、良く言えば「効率的」に、悪く言えば「雑」に
「よく理解できない箇所や間違えた個所だけを復習する」
という復習法も考えられます。
ただ、最初はほぼ全部よく理解できないし、間違えてしまうでしょう。
なので、初学者段階でこの手のショートカットはおすすめできません。
それか、合格目標を1年後ろ倒しするのもおすすめです。
たとえば、専業初学者なら、2月になっていたら翌年を合格目標にするのをお勧めします。
兼業初学者なら前年の11月でも次の次の合格を目指すべきでしょう。
※以下、択一で基準点を午前・午後のどちらかで超えられる人を「中上級者」、それ以外を「初学者」と定義。
※以下、週4日以上働いている人を「兼業」、それ以外を「専業」と原則定義。
ただし、未就学児がいる主婦(主夫)は「兼業」
松本雅典先生が5ヶ月で合格されていますが、1日17時間も学習されての合格であることを考えると、自分なら5ヶ月合格は難しいかもと思います。
既に行政書士を持っていたり、センスがある方なら別ですが。
1月中ならその年合格を目指すかどうかの本当にギリギリの瀬戸際だと思います。
兼業初学者なら、専業初学者よりも学習時間確保が困難なので、少なくとも1年は見たほうが基本的にいいです。
例外もいるのは、専業初学者の場合と同じです。
たとえばこのスーパーサイヤ人3さんは行政書士有資格者で、ぼくのブログの勉強法を真似て、独学7ヶ月で合格されています。






ちなみに、中上級者なら専業でも兼業でも年明けから十分合格は狙えます。
上記の基準から、直近の本試験合格を推奨されず、残念な気持ちの人もいるのではないでしょうか。
そんなあなたの直近合格を目標にしたい気持ちはわかります。
しかし、先を急ぐあまり「先に進むこと」が目的化し、身にならない勉強をしていたら力がつかないので本末転倒です。
腰を据えてじっくり取り組んだほうが結局早いこともあります。
たしかに
「今年合格を目指さないと来年合格はない。」
とよく言われ、それも一理あります。
しかし、その本質は、何が何でも直近合格を目指せというのではなく、
「今の段階から常に全力を尽くさないと、一生合格できない。」
ということです。
直近の試験合格を目指すのが明らかに難しい人もいます。
そんな人が直近試験で合格することを考えると、本当に無茶な計画を立てて「力をつけること」ではなく、「先に進むこと」が目的化します。
これでは仮に全範囲を終えても「頭に残らない」のは、あなたも想像がつきますよね?
もしかしたら、そうやって実際に失敗した人もいるかもしれません。
(というか、よく相談で聞きます。
「予備校講義についていったはいいけど、講義についていくのでいっぱいいっぱいで、復習ができず何も頭に残っていません。」
といったことを。)
このようにぼくが説明しても
「もう年だから1年でも早く受かりたい。
だから、俺は無謀であっても直近の合格を目指す!!!!!」
という方もいるでしょう。
しかし、1年でも早く受かりたいからこそ、地に足をつけて取り組む必要があります。
たとえば次の試験まで6ヶ月残っている場合に、兼業初学者が6ヶ月後の試験に向けて勉強するとどうなるでしょうか?
「先に進むこと」が目的化した勉強をすることになり、その6ヶ月は力がつかず貴重な6ヶ月をドブに捨てることになります。
そうすると、ほとんど初学者の状態で残りの1年の試験を戦わないといけません。
一方で、次の試験まで6ヶ月、次の次の試験まで1年6ヶ月あって、次の次の試験を目標に兼業初学者が勉強するとどうなるでしょうか?
地に足の着いた学習で、最初の6ヶ月も勉強できて力もつきます。
その力がついた状態で残りの1年でさらに力をつけて合格可能性を高めにいけるでしょう。
こんなふうに直近の合格を無理やり目指すゆえに最短合格が遠いたり、あえて合格目標年を遅らせることで合格可能性が上がったりします。
とにかく人それぞれ「最短合格」は違います。
「可処分時間が少ない人」や「勉強が苦手な人」が「可処分時間が多い人」や「勉強が得意な人」より合格まで時間がかかるのは仕方がありません。
- 足が速い人
- 足が遅い人
がいるのと同じ話です。
ちなみに、「効率的に勉強する」は当たり前の当たり前です。
みんな早く受かりたいので、あなたより「可処分時間が多い人」や「勉強が得意な人」もあなたと同じようにぼくの発信を見て効率的な勉強をしてきます。
「効率的な勉強をすれば、1日にたくさん勉強しないでも受かりますよ!」
「大事なのは時間(量)ではなく、効率(質)です(^^)」
「1日10時間とか勉強しないと受からない人はセンスがないので真似しないでください。」
といった耳当たりの良いことを言う情報発信者もよくいます。
そのほうがウケが良いからです。
しかし、ウケが悪くても、ぼくは『現実』をきちんとあなたにお伝えします。
質(効率)も大事だけど、量(時間)も大事だということを。
センスがある人は別なのでしょうが、それこそ凡人は「質(効率)オンリー」を真似したらダメですね。。
1日10時間以上勉強する方法については以下の動画で話しています。
とにかく
- 急がば回れ
- 急いては事を仕損じる
とも言いますが、地に足をつけて着実に行ったほうが遠回りのようでも近道です。
なので、合格目標年を1年ズラす勇気も時には必要だということを覚えておいてください。
これがぼくがこれまでたくさんの
- 司法書士受験生
- 行政書士受験生
- 司法試験・予備試験受験生
を見てきての結論です。
ただ、目標が遠いと人間はダレてしまいます。
ですので、目標点数を決めたうえでお試し受験をしたり、模試を適宜受けるようにしましょう。
>>【お試し受験をする人へ】受験料の元を取るためにやるべき3つのこと。【司法書士試験】
まとめ:復習はしすぎないようにしよう
話がちょっとそれましたが、以上のように学習初期でも狭いスパンの復習は2回に留めるのがおすすめです。
たしかに2回復習しても理解できない箇所も出てくるでしょう。
ただ、敢えて間を空けたり、他分野を学んだりすることで、スッと理解できることもあります。
そのため、同じ個所に固執するのはコスパが悪いし、まったくおすすめしません。
また、民法はいろいろな科目と繋がっていて、民法を忘れてしまうとほかの科目の学習に支障をきたすことがあります。
しかも民法は覚えることも多いし、配点も高い最重要科目です。
そのため、初学者のうちは民法だけはちょくちょくガッツリ復習するのはOKです。
※ある程度の実力者になってもぼくはガッツリとまではいきませんが、下記記事にあるように少しずつ毎日民法に触れてました。
>>【民法を最強の武器に!】ぼくがとった民法対策はこれです。【司法書士試験独学】
学習初期を終えた後の具体的な復習タイミングは翌朝に1回です。
詳細は下記動画をご覧ください。
おまけ:復習時間の比率目安
復習時間の目安としては、ぼくの経験則場は、全体の7分の1くらいに収まるのが良いと思います。
アウトプット重視段階の復習では「分散学習」が良いので、あまりにも復習時間がかかるなら、良く言えば「効率的」に、悪く言えば「雑」に
「よく理解できない箇所や間違えた個所だけを復習する」
というふうにしても良いと思います。
ちなみにぼくは予備試験論文の勉強をする際は、次の通りにしていました。
講義
↓
翌朝に前回の講義問題の解き直し、記憶事項の記憶
↓
その後は戻らずどんどん進めて1周したらまた解き直し
↓
翌朝復習
↓
繰り返し
前日の復習とその日の勉強の比率はだいたい8:1~6:1くらいです。
(つまり、最大でも7分の1くらいに復習時間を収めていました。)
上記にも書きましたが、初学者が1回目と同じくらい復習に時間がかかるのは多少仕方がないとも思います。
っていうか、1回目から何でもわかろうとしないことが大事で、
「2回目(明日)や3回目(明後日)で理解できればいいや~。」
という割り切りが大切です。
なので、そういった意味で割り切りにより1回目の時間が短くなって、2回目(1回目の復習)が1回目と同じくらいになるのはやむを得ないと思います。
とはいえ、1回目より2回目に時間がかかっていれば完璧主義に陥っている証拠です。
気を付けてください。
言語化が大変でしたが、参考になれば幸いです。
※本記事を見た人は下記記事も読んでいます。
 ︎この記事をシェアしませんか?
︎この記事をシェアしませんか?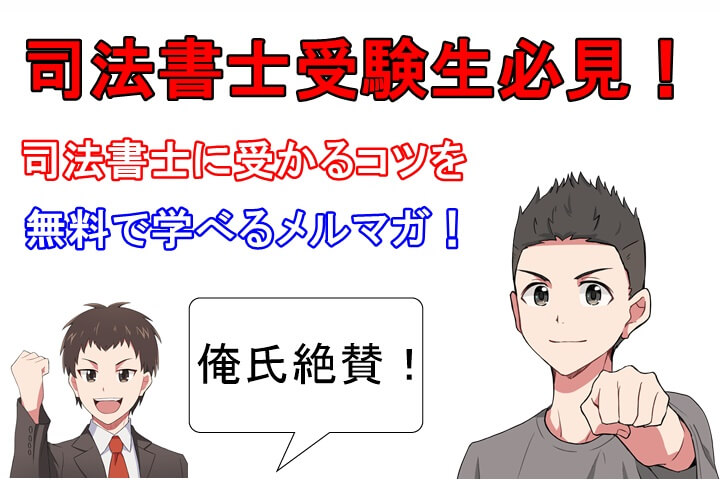






【司法書士試験独学】コロ助がとった択一の勉強法はこれです。【テキスト中心】の「テキストでインプット・アウトプット」で、“ また、復習するときはただ読みこんでインプットするのではなく、アウトプットもしていました。
テキストの重要なポイントを思い出しながら読むことによって、それがアウトプットになります。”とありますが、辰巳の松本先生が提唱する「テキストでアウトプットする勉強法」でしょうか?
それとも、もっと簡易な方法でしょうか?
コロ助さんがお忙しいのは重々承知してますが、もし可能であれば具体的にどのようなやり方であったのかお教え願えませんか?
とりわけ個人的にメールをお送りくださっても構いません。
よろしくお願いします。
辰巳の松本先生が提唱する「テキストでアウトプットする勉強法」です。
ぼくは下記記事にある通り、松本先生の5ヶ月合格法を読んで実践して合格しました(*^^*)
【保存版】司法書士独学でコロ助が使用したテキスト・問題集まとめ
書籍だけでなく、松本先生の以下の動画と記事も参考になります。
https://www.youtube.com/watch?v=726XjNaIj60
https://allabout.co.jp/gm/gc/440711/
[…] コロ助さん:オートマテキストとオートマでるとこに絞った勉強法。過去問はやらないという勉強法で22歳の若さで合格されています。 […]